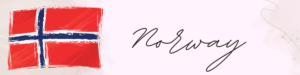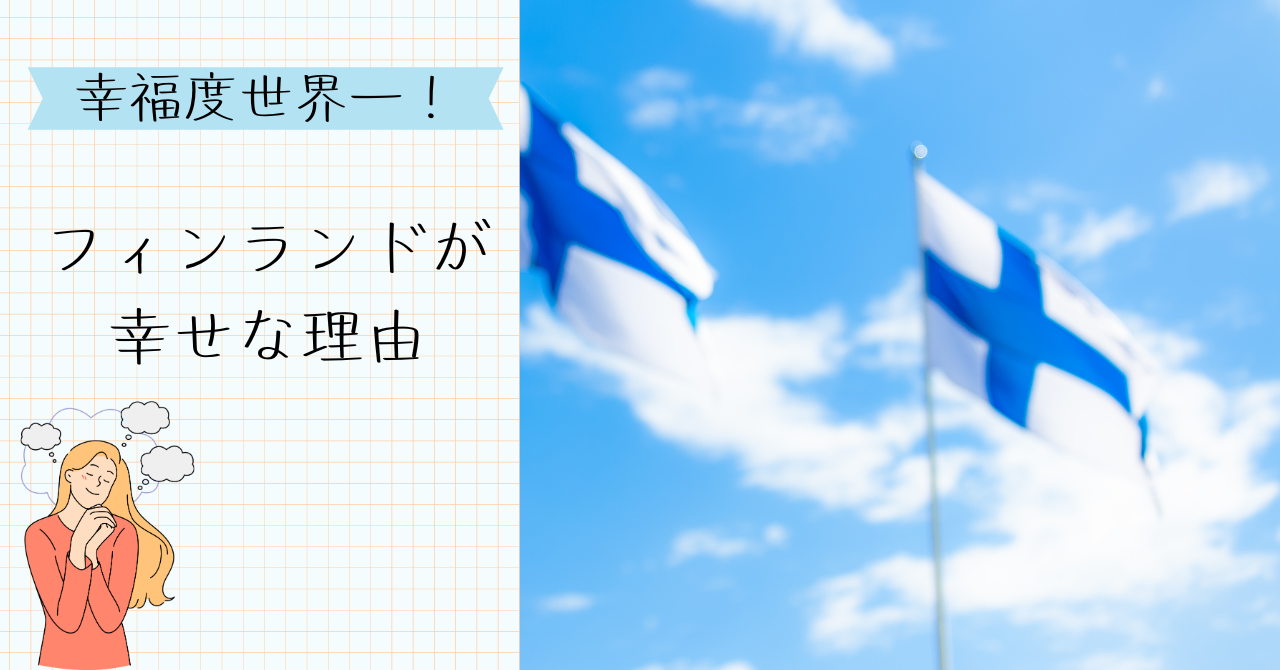北欧といえば、『世界幸福度ランキング』で毎年上位にランクインしているというイメージがありませんか?
なかでもフィンランドは、7年連続1位を獲得しています(2024年7月時点)。
2022年の世界幸福度ランキングでは、残念ながら我が国日本の順位は62位。
2023年では47位と少し順位が上がったものの、決して良い数字といえないことがわかります。
もっと日本の順位を上げたいところですが、そもそも1位のフィンランドと日本では何が違うのでしょうか。

世界幸福度ランキングとは
世界幸福度ランキングとは、アメリカの世論調査会社であるギャラップ社が収集したデータをもとに、国連の持続開発ソリューションネットワーク(SDSN)が統計分析を行い発行しているランキングデータです。
このランキングは毎年3月20日の「国際幸福デー」に合わせて発表されます。
世界幸福度ランキングは、以下の6つの指標に基づいて各項目をスコア化します。
- 国民一人当たりの国内総生産(GDP)
- 社会保障制度などの社会的支援
- 健康寿命
- 人生における選択肢の自由度
- 他者への寛容さ
- 政府や企業の腐敗の認識度
さらに7つ目の指標として、上記6つの項目がすべて最低値である「架空のディストピア社会との差分」をスコア化し、合計スコアの高い順にランキングがつけられます。
フィンランド人が幸せな理由5選
世界幸福度ランキングでは北欧諸国が毎年上位にランクインしていますが、なかでもフィンランドは6年連続1位を獲得しています。
「フィンランドは住みやすそう」という漠然としたイメージを持つ人も多いですが、これほど幸福度が高いことを示す数値を、長年にわたって維持し続けている秘訣はどこにあるのでしょうか。
次から1つずつ解説していきます。
世界で最も整ったワークライフバランス

2019年、ニューヨークのKISIという企業が東京を含む40都市を対象に行った調査で、フィンランドのヘルシンキが「世界で最もワークバランスの整った都市」に選ばれました。
東京と比べると、有給日数や育休日数が多く、通勤時間は少なめと、大きく差が出ています。
フィンランドには長時間の残業がほとんどありません。
朝8時ごろから始業し、夕方16時ごろには終業して帰宅します。
プライベートや睡眠、休養の時間をゆっくり取ることができます。
また、在宅勤務の割合も高く、通勤に時間を取られずに働いている人も多くいます。
長時間労働や場所に縛られることなく、自らのライフスタイルに合わせた働き方ができるという点が、個々人の幸福度につながっています。

こちらもCHECK
-
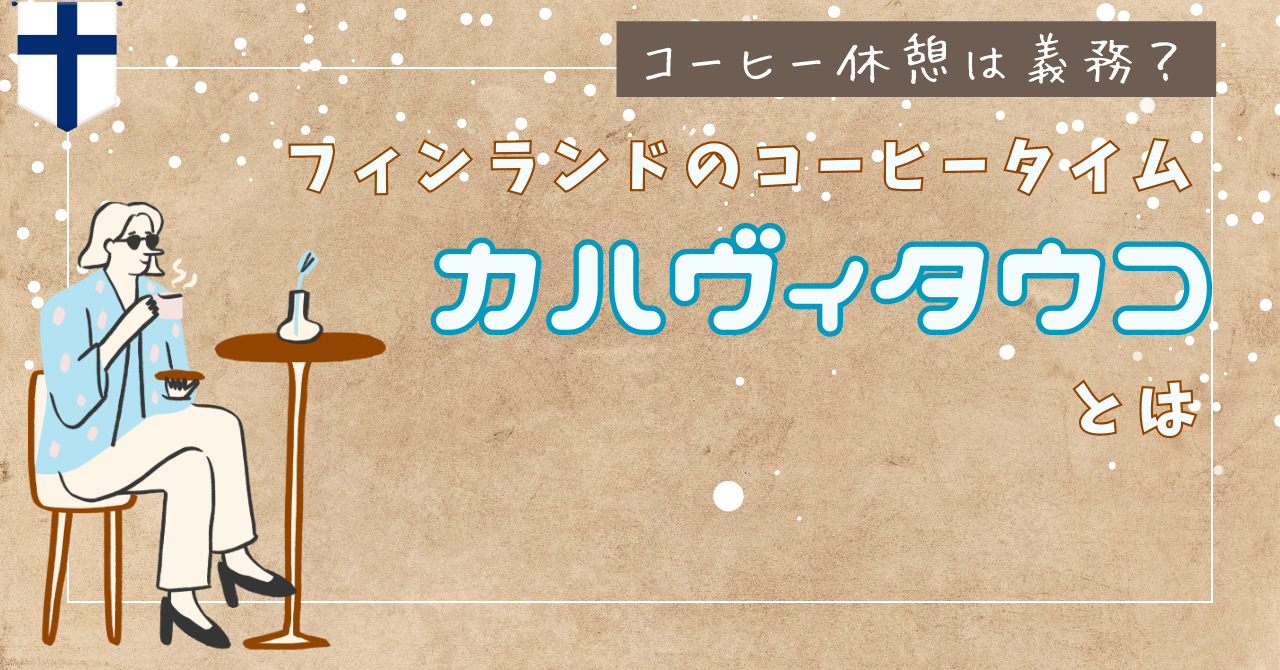
-
コーヒー休憩は義務?フィンランドのコーヒータイム「カハヴィタウコ」とは?
フィンランドでは仕事中にコーヒー休憩をとる光景がよく見られますが、この光景は日本でも見ることが多いのですよね。しかし驚きなのは仕事中のコーヒー休憩を設けることが労働者の権利として法律化されていることです。今回は、フィンランドのコーヒー事情について紹介していきます。
続きを見る
充実した社会保障

フィンランドの社会保障と聞くと、まず思い浮かぶのが「教育費が無料」という点です。
実際にフィンランドは子育てや教育に対するサポートがかなり充実しています。
まず、産休・育休は父親、母親どちらも取得することができ、休業中は所得の66%が補償されます。
そして就学前教育(プレスクール)から大学院までの学費が無料となっており、給食費は高校まで無料、教材費・通学費用は義務教育まで無料。
すべての児童が16歳になるまで、親の所得に関係なく児童手当が給付されます。
さらに、労働者に対する社会保障にも力を入れており、失業手当や、失業中の職業訓練に対する保障が充実しています。
失業手当は最長1年6ヶ月間、毎月約558ユーロ(日本円で約72,000円)支給されます。
さらに職業訓練として、フィンランド経済省の職業促進コースに参加すれば、追加の給付金が支給されます。
また、ヘルシンキ市では企業側にも失業者新規採用のための補助金を支給し、再就職支援を盛んに行っています。
「フィンランドは税金が高い」というイメージがありますよね。
フィンランドの社会保障負担率は約65%で、日本の負担率約42%と比べると「税金が高い」という印象を持つでしょう。
ですがその分、あらゆる世代や状況に対するサポートが充実しているため、不安なく暮らすことができ、それが幸福度につながっているといえます。
高い教育水準

フィンランドは「教育大国」とも呼ばれるほど、教育に力を注いでいる国です。
まず特徴的なのが授業スタイル。
日本をはじめさまざまな国で行われているような詰め込み型教育ではなく、生徒の自主性にまかせ、問題解決のためのサポートを教師が行うというスタンスで教育を行っています。
これにより、幼いころから「自分で考える」という習慣が身につき、思考力や問題解決能力を高めています。
教師にもかなりの裁量が与えられています。
授業要項が詳細に定められている日本とは異なり、教師が教科書を自由に選ぶことができます。

フィンランドでは、教師になるための資格として修士号の取得が必須です。
さらに、毎年研修があり、自らの教師としての質や専門性を高める努力が必要とされています。
子どもの能力や自主性を大切にしながら、信頼のおける教師と共に思考力を伸ばす教育をしているフィンランド。
日本の高校受験、大学受験のような受験制度もありません。
子どもも大人もストレスが少なく、幸福度が高い社会が形成できているといえるでしょう。
フィンランドの教育制度を詳しくCHECK
-

-
フィンランド教育、日本とどこが違う?特徴や制度を徹底解説!
近年、フィンランドでの教育が世界で注目を浴びています。学費無料や、生徒の個性を重んじる教育として有名ですが、実際にどのような制度や特徴があるのでしょうか。この記事では、高い学力を維持し続けているフィンランドの教育について紹介します。
続きを見る
政治における多様性

2019年、フィンランドで34歳の女性首相が就任したことが話題になりました。発足当時の女性閣僚は12人、女性の国会議員は2023年4月時点でも議会の約半数を占めています。
また、フィンランドでは、教師や運転手、郵便局の職員など、さまざまなバックグラウンドを持つ人たちが政治家に立候補しています。
日本では選挙に出馬するため60万円の供託金が必要ですが、フィンランドでは供託金は不要で、誰でも立候補しやすい環境となっています。
このように、政治の場において年齢や性別による格差がなく、多様性が担保されているからこそ、政治をより身近に感じることができます。
さまざまな立場の人たちの意見が反映されやすく、それが幸福度の底上げになっているといえるでしょう。
対して、2023年時点で日本政府における女性閣僚の数はたった3人と、G7のなかでも最も少ない割合となっています。

人生における自由な選択肢

育児や教育のサポート、社会保障、政治の多様性。
これらを充実させていくことは、ひいては人生における選択肢の自由さにつながっています。
お金やキャリアために出産をあきらめたり、失敗を恐れて転職や起業をあきらめたりせず、自分のやりたいことにチャレンジしやすい環境がフィンランドには整っているといえます。
「人生のレール」といった考え方はなく、社会人になってから大学で学びなおすことも普通です。
自分の意志でどう生きるかを決められるからこそ、人生をのびのびと楽しむことができ、幸福を感じることができるのではないでしょうか。
まとめ
今回は、『世界幸福度ランキング』6年連続1位のフィンランド社会について紹介しました。
人生における選択肢が豊富で、社会保障が手厚いからこそ、自分に対して、それから他者に対しても寛容になることができます。
寛容さを持ち、お互いに尊重しあえることは幸福度の第一歩であるといえるのではないでしょうか。
日本もフィンランドもどちらも素晴らしい国ですが、日本がフィンランドに学べるところはたくさんあります。

フィンランドの社会についてこちらもCHECK!
-
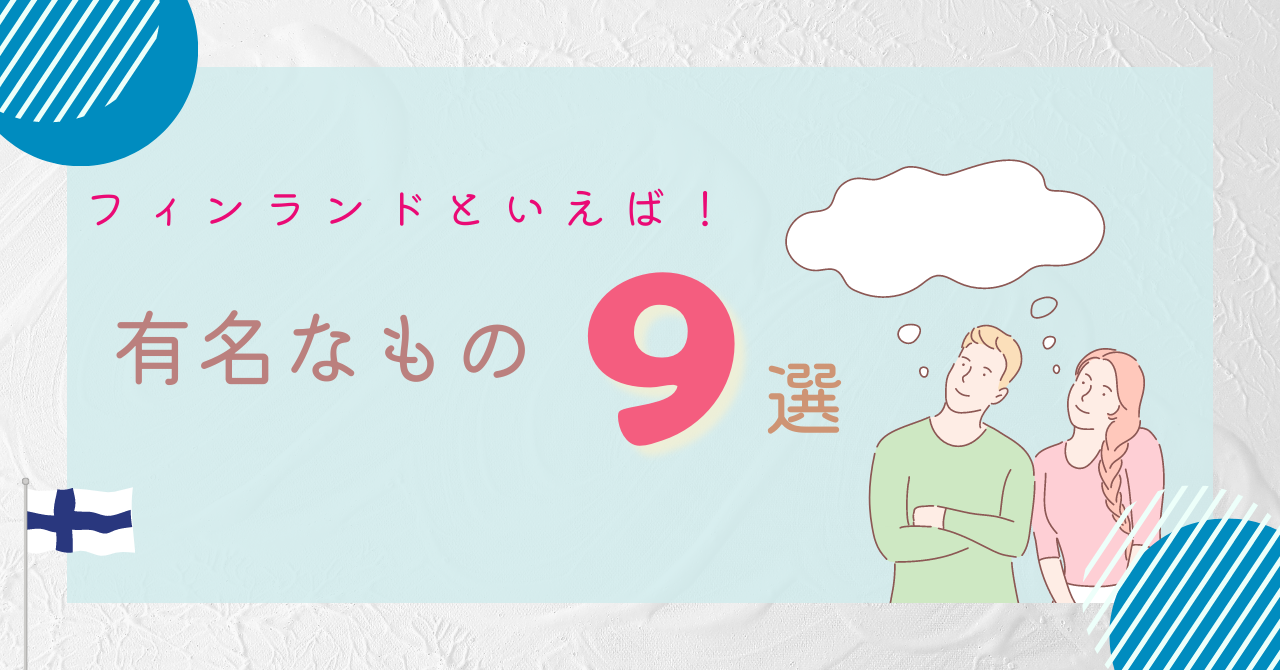
-
幸せの国!フィンランドが好きになる世界的に有名なもの9つを紹介!
フィンランドは、一度訪れたら忘れられないほど人を惹きつける魅力あふれる国です。世界中にリピーターも多く、日本からは最も近いヨーロッパの国の一つとしても人気があります。フィンランドが世界中の人々を魅了する有名なものにはどんなものがあるのでしょうか?日本人にもなじみのあるものも多いので、要チェックです!
続きを見る
-

-
フィンランドで就職したい!まずは語学学校に通うのが良い?
世界有数の福祉国家であり、世界一幸せな国としても知られるフィンランド。フィンランドの美しく豊かな自然や、おとぎ話の世界のような街並みに憧れ、住んでみたいと思う人もいるのではないでしょうか。いざ移住となると、言葉の壁が最初のハードルになります。フィンランドで就職する前に、語学学校に通ってフィンランド語を習得する必要があるでしょう。今回は、フィンランドでの語学学校から就職するまでの流れを説明していきます!
続きを見る
-

-
日本と共通点の多いフィンランド、知っておくべき10個のマナーをご紹介
日本と距離は離れているフィンランドですが、フィンランド人は「ヨーロッパの日本人」と言われるほどいくつもの共通点があります。しかし、やはりフィンランドはヨーロッパの国であり、日本とは異なるマナーもあります。そこで今回は、フィンランドで知っておくべき10個のマナーを紹介します。
続きを見る
-

-
フィンランドの歴史からたどるロシアとの関係
2023年4月4日、NATOに正式加盟を果たしたフィンランド。中立の立場を守ってきたフィンランドの歴史を大きく変える出来事となりました。ロシアとの関係は更に緊張状態が強まり、今後の動向に世界中から注目が集まっています。今回は、そんなロシアとフィンランドの関係を歴史から紐解いてみたいと思います。
続きを見る